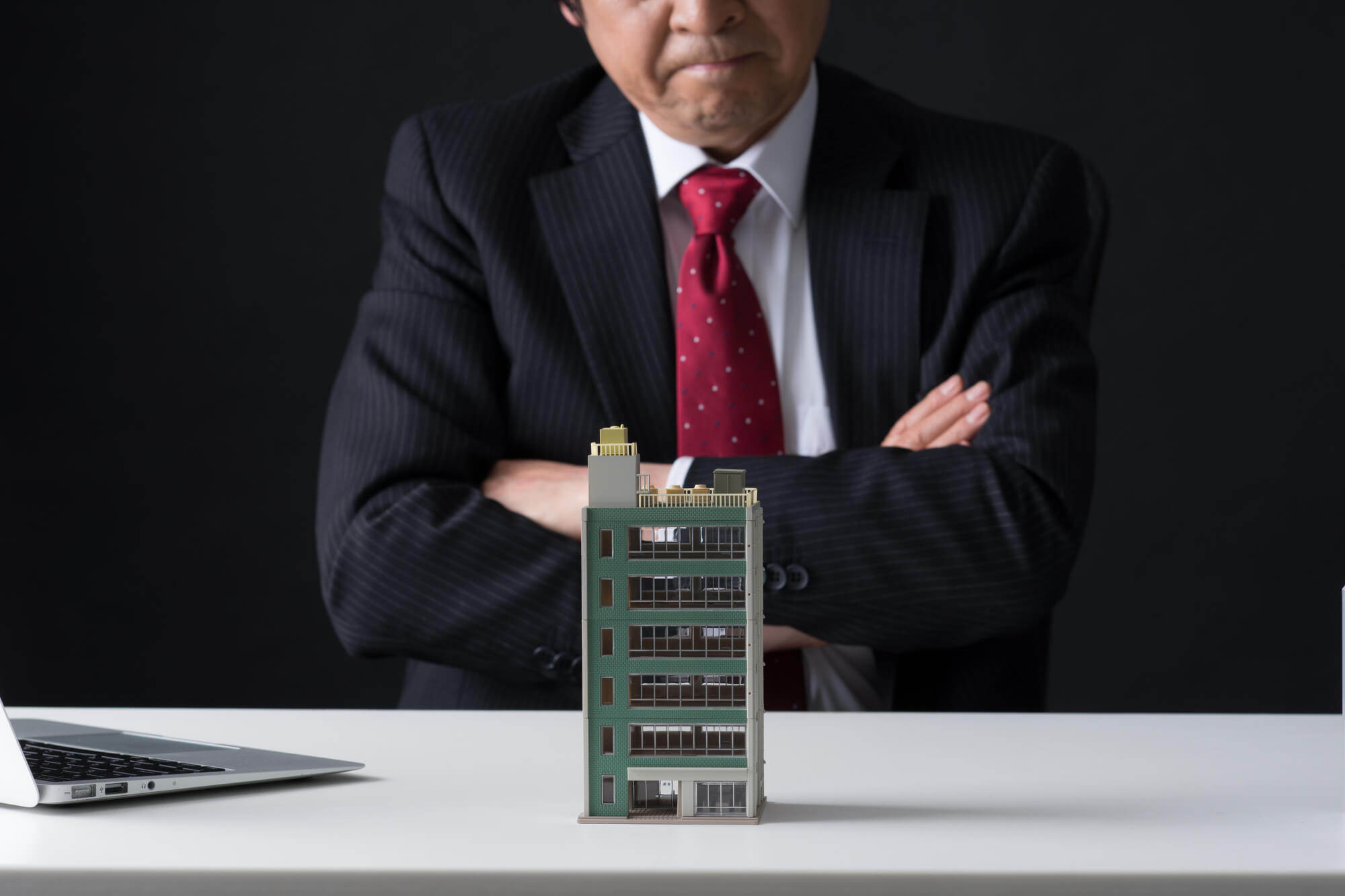遊休不動産の活用(3)~遊休不動産の活用方法~
遊休不動産の活用について考えるシリーズ。第3回は遊休不動産の活用方法を紹介します。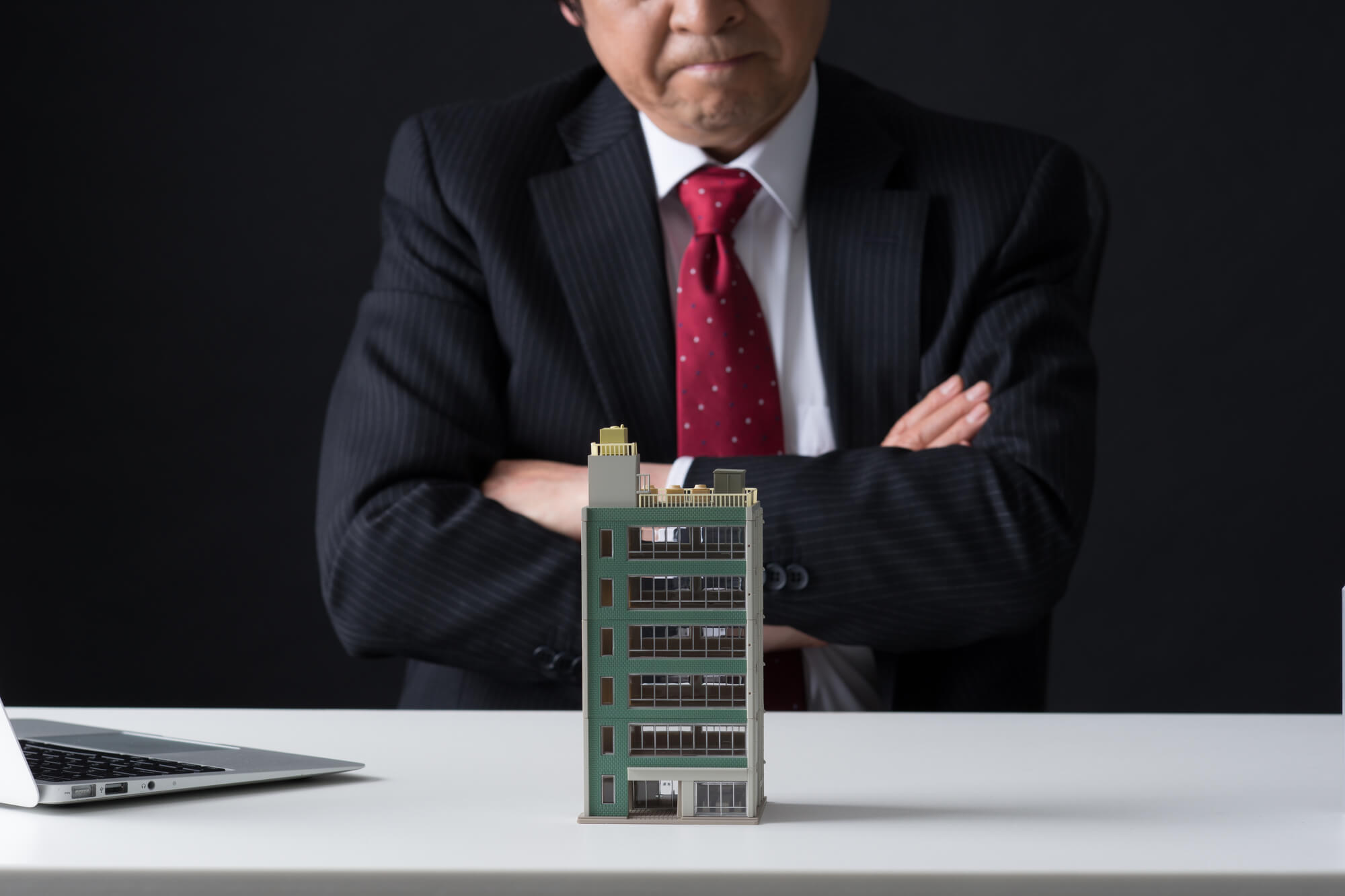
売却はデメリットの少ない活用方法
「売ってしまうことが活用方法なの?」と思うかもしれませんが、実は最も手軽かつリスクやデメリットの少ない活用方法なのです。
所有する不動産に思い入れがあったり、将来その土地で暮らしたいというケースもあるでしょう。しかし、放置して荒れ果ててしまった建物や土地を整備して再び使えるようにするには、費用と手間がかかります。
また、将来活用するときまでの固定資産税や都市計画税の出費もあります。それならば、すぐに活用する意思のある人に売却してしまうというのが、自分にとっても地域にとっても有効な手段になります。
この不動産の活用というのは、基本的に投資をするのと同じことです。そして、リスクのない投資はありません。また、所有している不動産が遊休化しているということは、活用に手間暇をかける余裕がないということでもあります。
知識も余裕もない人が行なう投資は、よりリスクが高まります。活用に失敗すれば、大事な資産を失うことにもなりかねません。10年先、20年先にその土地で暮らしたいのであれば、売却して得た現金を蓄財しておき、移住したいと思ったときにあらためて不動産を購入するほうがずっと効率的なのです。
建物があるなら賃貸を考える
売却が有効手段とはいえ、やはりどうしても売ってしまいたくないという人も多いでしょう。敷地内に先祖伝来の木が植えてある、近くに親類縁者が住んでいて売却に難色を示される、というような事情があるケースも考えられます。
こうした場合、所有する不動産に建物がある場合は、賃貸に出すことがもっとも多い活用方法です。将来自分が住むつもりの住居の場合、人に貸すことには抵抗があるかもしれませんが、住居は人が住んでいないほうが手入れがされず傷みやすくなります。
地方や郊外などで交通に不便な場所のケースや、建物が老朽化している場合などは、それほどの賃貸収入は期待できないかもしれませんが、固定資産税と都市計画税分がまかなえる程度になれば賃貸に出すメリットは十分あるといえるでしょう。
更地の場合は駐車場が最も手軽な活用方法
建物がない土地を所有している場合は、駐車場にするのが最も手軽な活用方法です。駐車場の契約には借地権などが発生しないため、契約の解除が比較的容易で、売却したり本格的な活用をする際の転用を楽に行うことが可能です。
駐車場には区画線などの最低限の設備で済ませる青空駐車場と、コインパーキングや立体駐車場のように本格的な設備を導入するタイプが考えられますが、将来別の活用方法を考えている場合は青空駐車場がおすすめです。
特に大都市への通勤圏内の住宅地では青空駐車場の需要が高く、高い収益は期待できませんが、税金分程度はまかえることが多くなっています。通勤圏から外れた田舎の土地の場合は、需要が期待できないため、ほかの活用方法を考えたほうがいいでしょう。
賃貸経営で安定的な活用を目指す
立地条件によりますが、ある程度の広さのある土地の安定的な活用を考えるなら、アパート・マンションや、オフィスビルなどの賃貸経営が適しています。
一般的にアパートなどの賃貸住宅のほうが、利益率は低くなりますが、景気に左右されにくいため安定的な運用が期待できます。
ただし、経営である以上リスクはあります。昨今は賃貸住宅経営の分野で多くの不動産会社が「一括借り上げ・家賃保証」などをうたったサービスを提供しており、オーナーは管理の手間もなく、家賃収入が減るリスクもなく賃貸住宅経営ができるかのように思えますが、必ずしも全てのケースでうまくいくとは限りません。
例えば、一括借り上げ・家賃保証であっても、10年毎などに保証額の見直しがある契約などもあり、保証額の減額によって建築費用のローンよりも家賃収入が下回り、経営が破たんする恐れがあります。
こうしたリスクを承知したうえで、経営のノウハウを学び、自分自身で経営が成り立つかどうかを判断できる人でなければ、安易に賃貸経営に乗り出すべきではないでしょう。
「遊休不動産の活用」はこちら↓
(1)増加する遊休不動産と問題点
(2)遊休不動産がマイナス資産と化す時代
(3)遊休不動産の活用方法
(4)管理・活用を支援するサービス
(5)遊休不動産活用を支援する施策
「関連記事①-自社ビルか賃貸か」はこちら↓
(1)自社ビルのメリット
(2)自社ビルのデメリット
(3)賃貸のメリット
(4)賃貸のデメリット
(5)財務面の影響とこれまでのまとめ
「関連記事②-持ち家か賃貸住宅か」はこちら↓
(1)支出を比較する方法
(2)持ち家の維持・修繕の実際
(3)35年後の資産価値
(4)賃貸住宅における原状回復の範囲
(5)最終結論